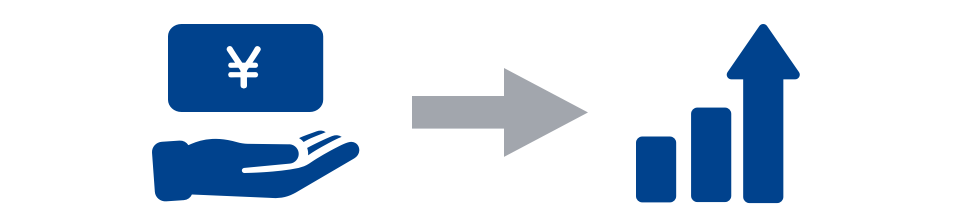2.1 気候変動政策の課題
パリ協定の採択とその後の交渉
2015年末の気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定は、世界の気温上昇を産業革命前の水準から2℃よりもはるかに低い水準に止め、さらに1.5℃に止めるよう努力すること(第2条)、またそのために、世界の温室効果ガス排出量を可能な限り早期にピークを迎え、その後急速に削減し、今世紀後半には、排出を実質的にゼロ(人為的な排出と吸収をバランスさせる=ネットゼロ)にすること(第4条)を目標に定めた[1]。このように国際協定として気候変動を防ぐための長期目標を初めて明確化したパリ協定は、各国が協調的かつ積極的に行動することの必要性を国際社会が広く共有した歴史的な合意となった。また、米中の二カ国を始めとする各国が迅速に批准手続きを進めたことにより、パリ協定は、その採択から1年に満たない2016年11月6日に、55カ国以上の批准と55%以上の世界の推定総排出量という要件を満たし、発効した。採択から発効までに7年余の月日を要した京都議定書と比べれば圧倒的な早さである。
パリ協定は、2条・4条の目標の達成のために、各国に対し、国別約束(Nationally Determined Contributions: NDCs)の5年ごとの提出を義務付けている。NDCには、緩和に関する目標や行動のみならず、適応、資金、技術移転、能力構築などについても情報提供を求め、透明性の高い仕組みで、世界の気候変動政策の包括的な管理を目指すものである。各国には、削減目標の達成自体は義務付けられていないが、NDCの提出と政策措置の実施が義務付けられている。この仕組みでは、各国の目標や行動が、気温目標や今世紀後半に実質的に排出をゼロにすることに照らして十分かどうかという厳格な評価と、各国からの的確な情報の提出と、行動を引き上げる協議の仕組みが鍵を握っている。
2018年のルールブック完成と促進的対話
2018年は、パリ協定のルールブックを完成させること、さらにそこに向けて世界全体での行動について確認するための促進的対話(facilitative dialogue)の実施が予定されている。現在は、パリ協定特別作業部会(Ad hoc Group on the Paris Agreement: APA)において交渉が続けられており、2018年12月にワルシャワ・カトヴィツェで開催予定のCOP24で、パリ協定の下で各国が行動を実施するための詳細なルールを決定することが目指されている。決着をつけるべき議題は詳細にわたり、年末に向け交渉が重点化されていく見込みである。また、促進的対話(COP23議長国フィジーの伝統的な対話方式の表現を用いて「タラノア対話」と呼ばれるようになった)は、世界の気候変動対策を前進させるためのプロセスであり、2017年のCOP23では、準備フェーズ(政府やステークホルダーからのインプットを受けて情報や証拠を整理)と、政治フェーズ(閣僚級の代表による気温目標達成に対する各国の進捗を確認しNDCの準備に活用)の2段階で、2018年1月から1年間にわたって実施することを決めた。現在各国がパリ協定前に提出した約束草案(Intended Nationally Determined Contributions: INDC)では、1.5~2℃未満に気温上昇を抑制するためには全く足りないことが明らかになっており、とりわけ気温上昇を1.5℃に抑制しようとする場合は各国はさらに大胆に行動を引き上げ、急速に排出を減らしていかなければならず、この1年間のタラノア対話は、その事実を各国で再認識し、2019年の最初のNDCの提出の機会に行動を引き上げることにつなげる上で決定的に重要なプロセスとなる。
世界のトレンド-脱炭素化経済への転換の加速
パリ協定には2018年1月末現在で、197カ国が署名、174カ国が批准を済ませている。2017年1月に誕生したアメリカのトランプ政権は、オバマ前政権の方針を翻し、パリ協定からの離脱を表明したが、これまでのところそれに追従する国は一つもない。
逆に、パリ協定を機に、企業や投資家、地方自治体などによる脱炭素化への転換のネットワークやイニシアティブが加速している。アメリカでは、トランプ大統領の方針に抗し、「WE ARE STILL IN(それでも我々は(パリ協定に)留まる)」というムーブメントが拡大し、これまでに米国のビジネス、自治体、教育機関、 宗教者などのリーダーなど2500の団体が名を連ねている[2]。もう一つの大きな動きは、イギリスとカナダが主導する「脱石炭へ向けたグローバル連盟 (Powering Past Coal Alliance)」の発足である。この連盟は、国内の石炭火力発電所の新規建設の停止、既存の石炭火力発電所の段階的全廃、さらに途上国への支援の停止という方針を定めた宣言に合意しており、脱石炭への大きな国際的なうねりを作り出している。COP23の発足の発表のときには、27 の国と都市が名を連ねていたが、翌12月にフランスのマクロン大統領が主催したOne Planet サミットにおいてさらに7つの国と州・地方都市が加わり、その数は34となっている(さらに20の民間セクターも参加している)。同連盟は、来年 2018 年のCOP24カトヴィツェ会議にはこれを 50 に増やすことを目指している。
国内の2030年の目標設定と政策方針
日本では、京都議定書第1約束期間(2008~12年)の日本の取り組みとして地球温暖化対策推進法の下で京都議定書目標達成計画が定められていたが、2012年度にその期間が終了した後の計画が策定されておらず、空白期間が続いていた。その背景には、2011年3月の東日本大震災と福島第一原発事故や政権交代などにより、気候変動政策への政治的関心が大きく低下したことがある。2012年に復活した自民党政権は、民主党政権が決定した「革新的エネルギー・環境戦略」や2020年25%の温室効果ガス排出削減目標(1990年比)を白紙撤回する方針を示したものの、その作業にすぐに着手せず、2012年度末に計画が終了する時には、「切れ目なく対策を推進し、これまでと同等以上の対策を求める」と決定しただけだった[3]。さらに、実質的な議論がないまま、政府は官邸内だけの協議により、2013年11月のCOP19において、原発の稼動をゼロと仮定した場合の暫定目標「2020年3.8%削減(2005年比)」を発表した。その水準は、京都議定書の6%削減よりも緩く、排出増加を容認する低いものであったが、その目標は、暫定目標のまま店ざらしにされた。2030年目標については、政府はCOP21パリ会議前の2015年7月に、2030年の温室効果ガス排出削減目標を26%(2013年度比)とする方針案をINDCとして決定し、国連に提出していた。これは2030年のエネルギーミックスを基本にしたもので、2030年においても原発(20~22%)や石炭火力(26%)に引き続き大きく依存する電源構成を前提としたものであった。
政府がこれらの目標を含め、国内の対応を正式決定したのは、COP21でパリ協定が採択された後になってからである。政府は、京都議定書目標達成計画後から3年2ヶ月の空白期間を経てようやく、2016年5月に地球温暖化対策推進法に基づく地球温暖化対策計画を閣議決定し、同計画において、2020年3.8%削減,2030年26%削減を国の目標としてそのまま正式に決定した。
なお、温室効果ガス排出量の推移については、福島原発事故後に化石燃料依存の高まりによって2011年以降増加が続いたが、2013年度をピークに減少傾向に転じている。原発のほとんどがなお停止しているにもかかわらず減少に向かった背景には、民主党政権下で導入されたFIT法の効果や、企業や個人の省エネが進んだことが寄与していると分析されている。2012年に大きく弱められた2020年の暫定目標は、2015年時点で既に超過達成しており、目標としての機能を失っているが、目標の引き上げ議論は全く起こっていない。
建設が進む多数の石炭火力発電所
日本では、福島原発事故後の2012年から、多数の石炭火力発電所の建設計画が立ち上がり、その数はこれまでで50基(2332万kW)に上る。このうち、2017年末までに5基(61.2万kW)が稼動を始めたが、2017年には4基(231.2万kW)の計画中止が発表された。中止されたのは、関西電力が石油からの燃料転換を計画していた赤穂発電所(60万kW×2基)、関電エネルギーソリューションと東燃ゼネラル石油が千葉県に計画していた市原火力発電所(100万kW)、前田建設が岩手県に計画していた大船渡港バイオマス混焼石炭火力発電所(11.2万kW)で、それぞれの中止理由は異なるが、省エネの進展や、電力需要の減少、パリ協定などのCO2制約の強化などの経営環境の変化が挙げられており、事業者の中には立ち止まって計画を見直すところも出てきた。しかし中止案件は計画全体の1割に過ぎず、残るほとんどの計画は順調に環境影響評価手続きを進め、建設着工へと進んでいる[4]。
パリ協定の目標の1.5~2℃目標の達成には、新規はもとより、既存の石炭火力も、CCS(二酸化炭素固定貯留化技術)を備えていない限り、急速に減らさなければならず[5]、先進国は2030年には石炭火力ゼロを目指さなければならない。パリ協定後は、国際的に、石炭火力からの撤退の必要性がさらに強く認識され、先進国で日本のように石炭火力発電所を建設しようという国はもはやほとんどない。中国やインドでも再生可能エネルギーが急速に伸びる一方で、石炭火力の建設計画の多くが頓挫している。さらに、先に紹介したように脱石炭の国際連盟のような動きも出てきた。そのような中で、日本が、パリ協定に完全に矛盾する石炭火力をなお推進しようとしていることは、世界の中でも際立って問題視される動きになっている。
日本の気候変動政策の課題
日本の気候変動政策の課題として、削減目標水準、石炭火力推進を含むエネルギー政策方針、長期戦略について最後に取り上げる。
まず削減目標の水準について、2016年5月決定の地球温暖化対策計画に規定された2020年・2030年目標は、いずれも極めて低い水準に留まり、各主体の気候変動対策を牽引し、さらにパリ協定の目標達成に向けた日本の応分の行動として不十分なものである。2020年からのパリ協定の実施に向け、2019年にNDCを正式に提出する際には日本は、その目標水準を引き上げることが必要であろう。また、石炭火力発電について、現在もなお40基、2000万kW以上の建設計画が動いていることを差し止める必要性がある。これらが建設されれば、石炭火力の設備の寿命を2050年より先に引き伸ばし、日本の脱炭素化を困難にすることになるため、早急な政策判断が求められる。そのためには、原子力と石炭火力を「ベースロード電源」と位置付けて優先付けするエネルギー基本計画の基本方針を、再生可能エネルギーを軸にした柔軟で分散型のエネルギーシステムへと転換することが必要である。最後に、政府はパリ協定に基づく2050年までの低炭素排出長期戦略の策定を2018年度中に準備していることから、その検討において、2020年・2030年目標の引き上げとともに行い、2050年に向けた着実な温室効果ガス排出削減に向けた排出経路を描く作業に取り掛かる必要がある。
なお、今日の2012年以降の気候変動政策プロセスや目標設定のプロセスは、情報の公開や参加の機会が大きく減じられており、エネルギー政策を講じる経済産業省・資源エネルギー庁の一方的な決定に独占されているが、以上の検討と方針の決定は、これからの日本の国づくりや経済・社会の方向性などを決定付ける市民に大きく関わる問題である。市民参加、情報公開の下で実施すべきことであることは言うまでもない。
(気候ネットワーク 平田仁子)
[1] UNFCCC, Paris Agreement
[2] https://www.wearestillin.com/
[3] 地球温暖化対策推進本部「当面の地球温暖化対策に関する方針」 2013年3月15日
[5] UNEP, 2017, “Bridging the Gap – Phasing out Coal”, The Emission Gap Report 2017, Chapter 6.